トップ
お知らせ
-
2024.04.09
展示会のお知らせ
奥順/石下結城紬展 「もうひとつの結城紬」
本展は石下結城紬という絹織物を単独で紹介する、はじめての展示会です。
石下は鬼怒川沿いの茨城県常総市に位置し、古くから日常の衣服を織ってきた産地です。すぐそばに紬の原型を残す本場結城紬の産地があり、地理的にも品質的にもその周辺として位置づけられながら、職人の手仕事と機械動力の協業による独自の伝統技術を育んできました。しかし日本の伝統織物において、動力を取り入れた産地の情報はごくわずかです。結城紬に関しても、そのほとんどは本場結城紬の紹介に限られています。
手仕事と機械動力は、ものづくりの現場ではへだてなく共存しています。手仕事の多くは道具を使い、動力もまた道具のひとつだからです。伝統工芸においては、周辺に位置する産地こそ、新しい技術を積極的に取り入れてきました。とはいえ石下の産地では、動力を用いる工程を含め、ほとんどが熟練の職人による仕事です。結城紬というしっかりとした輪郭があり、そこを質的に変えてしまうほどの変化を拒んできたからです。
本展では石下結城紬の製作工程を丁寧に紹介することで、原始的な手仕事を守る本場結城紬とは異なる歴史をたどった「もうひとつの結城紬」のかたちを示します。結城紬という特定の産地織物についての展示ですが、各地の工芸産地についても視座を与える内容だと思います。あわせて石下結城紬の新作を展示致します。
----------
奥順/石下結城紬展 「もうひとつの結城紬」
日時/2024年5月9日(木)-12日(日)
10:00-19:00(最終日のみ17:00まで)
会場/代官山ヒルサイドテラスE棟ロビー
展示品の販売は致しません。
会期中、職人による実演を予定しています。
詳細は当HP、Instagramにてお知らせします。
企画協力・グラフィックデザイン/山口信博+玉井一平 -
2024.03.11
糸つむぎ講習会のお知らせ
奥順では本場結城紬の糸取り手を育成する講座を2018年より実施してきましたが、この度、湯本糸綿店の湯本正直さんを格子に迎え、新たに「糸つむぎ講習会」をスタートします。
ご興味のある方はお気軽にご参加下さい。
----------
\ 2024年4月スタート 毎月第1金曜日開催 /
「奥順/糸つむぎ講習会」
日時/初回 2024年4月5日(金)13:00-15:30
会場/つむぎの館 壱の蔵(奥順株式会社内)
講師/湯本糸綿店 湯本正直氏
参加費/無料 ※要予約
予約・お問合せ/tel.0296-33-5633 (火・水曜定休日以外の10:00-17:00)
※12:45より会場で受付を行います。開始10分前までにお越しください。
※個別レッスンのご予約も随時お受けしています。
----------
袋真綿を「つくし」と呼ばれる道具に
からませ、指先を使って繊維を引き出し、
糸をつむいでいきます。
撚りのない手つむぎ糸は空気をふくむため
軽くてやわらかく、比類ない着心地と
風合いを生み出します。
本場結城紬を特別なものにしている
この手つむぎ糸は今、不足しており、
本場結城紬の産地製造問屋「奥順」が
糸取りさんを育成する講習会を開催します。
糸つむぎを一緒に学んで、
「手つむぎ糸のあるくらし」をしてみませんか。
はじめての方には一から丁寧にお教えします。
すでに糸取りさんとして活躍されている
経験者の方も大歓迎です。
ブラッシュアップとしてお越しください。
ご興味のある方はお気軽にご参加ください。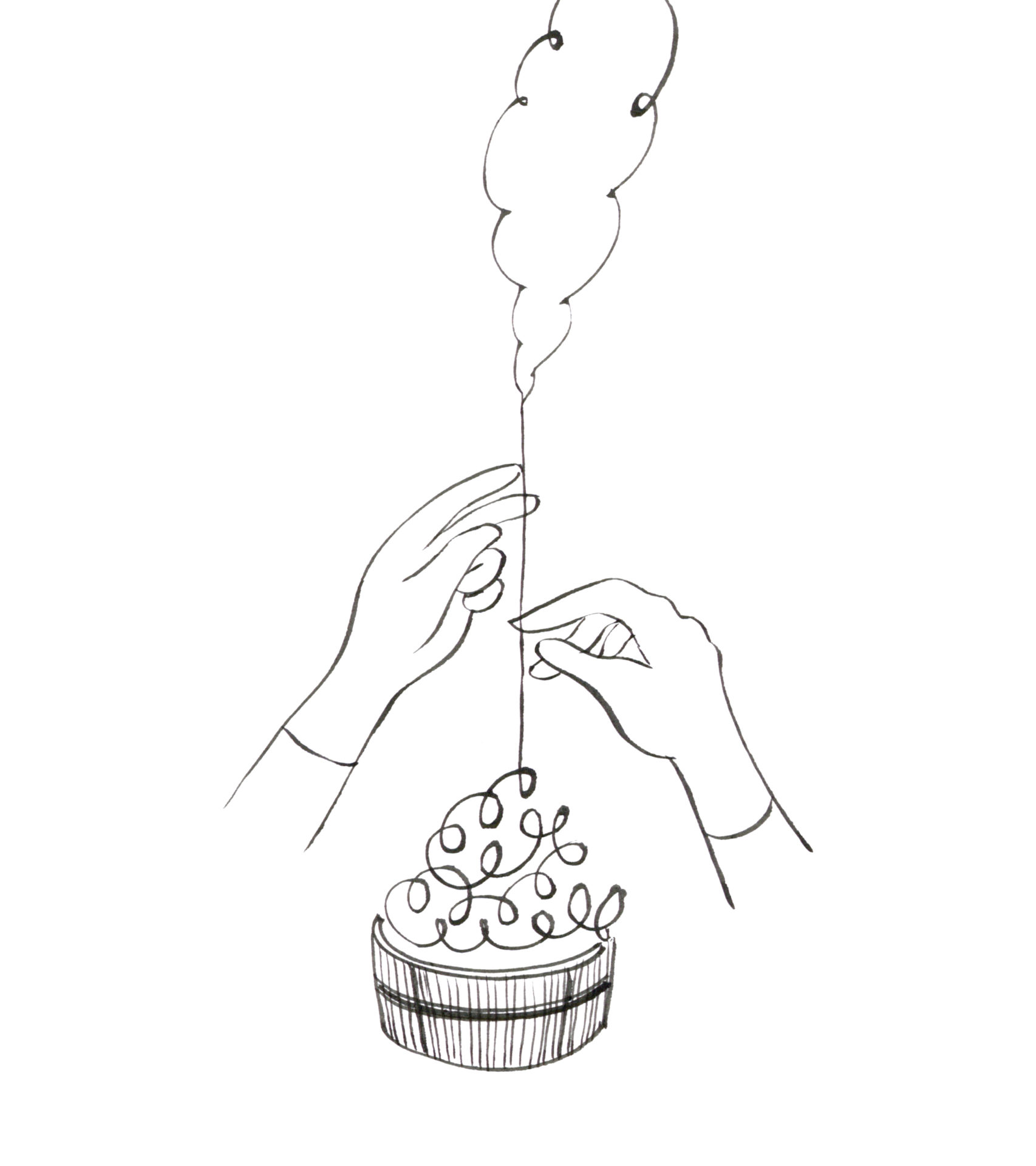
-
2024.03.01
メディア掲載/きものサロン2024年春夏号
『きものサロン2024年春夏号』所載の「浅田真央さんのきもの修行 結城紬」のなかで、浅田真央さんに結城紬の産地を訪ねて頂きました。弊社の本場結城紬もご着用頂いております。ぜひご一読下さい。
(p.118-p.125)
また特集「春色きもの花きもの」にて弊社の本場結城紬を掲載して頂いております。合わせてご高覧頂けたら幸いです。
(p.37、p.44)

-
2024.02.20
メディア掲載/美しいキモノ2024年春号
『美しいキモノ2024年春号』にて、弊社の石下結城紬を掲載して頂きました。
昨年リニューアルした石下結城紬の新商標も合わせてご紹介頂きました。
(p.144、p.145、p.150)
今回の『美しいキモノ』では、「再発見、いしげ結城紬」(p.143-p.150)という特集のかたちで、石下の産地を詳細に紹介して頂いております。ご一読頂けたら幸いです。

-
2023.12.31
ホームページ・リニューアルのご案内
弊社・奥順のホームページをリニューアル致しました。
-
2023.12.18
美の小壺『結城紬/化粧筆』が再放送
NHK福祉番組 手話で楽しむみんなのテレビ×美の小壺『結城紬/化粧筆』が再放送されます。
◎手話で楽しむみんなのテレビ/NHK
初回放送日/2022年12月21日
再放送予定・Eテレ/2024年1月6日(土)11:50~11:59
奥順について
奥順は明治40年の創業以来、産地製造問屋として、結城紬の図案制作、機屋への発注と仕入、流通を担ってきました。原料である糸の確保、反物の最終仕上げである湯通し(糊抜き)も自社で手がけています。また資料館を含む観光施設の運営、ショールをはじめとする新商品の開発など、結城紬を広く伝えるための事業を展開しています。

本場結城紬
本場結城紬は、糸つむぎから機織りに至るまで古来の技法が多く受け継がれている、日本を代表する絹織物です。最大の特徴は真綿から手でつむぎだす糸にあり、やわらかく空気を含んだ風合いは結城紬にしかない着心地を生み出します。四十以上にも及ぶ工程は分業によって担われており、一反の制作には何人もの職人が関わっています。関東平野を流れる鬼怒川流域を中心に、茨城県結城市から栃木県小山市にかけて生産されています。

石下結城紬
石下結城紬は、結城紬の最大の特長である真綿の風合いをより多くの方に楽しんでもらうために生まれた、もうひとつの結城紬です。 石下は鬼怒川沿いの現茨城県常総市に位置し、古くから着心地の良い日常の衣服を織ってきた産地です。すぐそばに本場結城紬の産地があり、その影響を受けながら、職人の手仕事と機械動力の協業による独自の伝統技術を育んできました。

着物以外の展開
結城紬をふだんの暮らしの中で使っていただけるように、着物以外にもさまざまな生地を展開しています。用途によって糸使いや仕上がりを変えることで、従来の結城紬にはない新たな表情の生地が生まれています。

お手入れ
結城紬は着こむほどに味わいを増し、水を通すごとに艶を増していく布です。 湯通し、洗い張り、仕立て替えなど、きちんとしたお手入れをすれば、長い年月をかけて風合いを育てていくことができます。

記事
結城紬と奥順について、伝えたいこと、記録しておくべきことを記事にしていきます。



